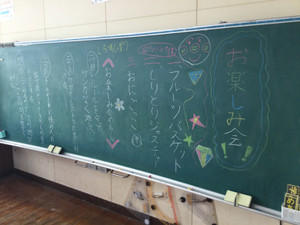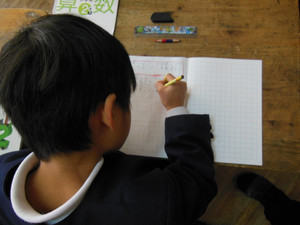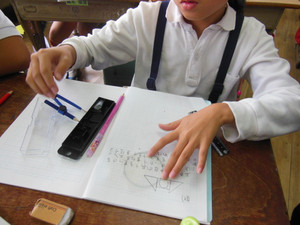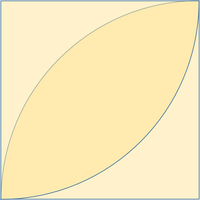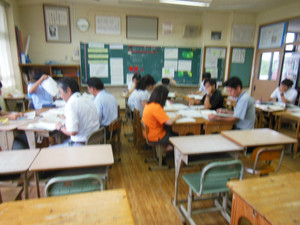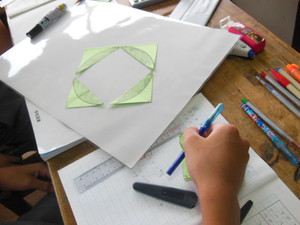第1回 かじきっ子見守り委員会(その②)
第1回かじきっ子見守り委員会のグループワークを終えた後の出席者の感想の一部をご紹介します。
○「もやもやした気持ちを暴力や仲間外れ,悪口などで解消しようとしない。」ということを学校だけでなく,保護者も普段から指導し続けることが必要。
○「相手がいやがることをしない。」という大前提を家庭や学校教育の中で子供たちに浸透させていくことが大切だと改めて感じた。
○ただ単に仲直りをさせるだけでなく,いじめをした子供自身が「悪いことをしてしまった。」と心から思えるように指導することが大事。
○いじめた側,いじめられた側の保護者の気持ちになって子供のことを考えると,保護者として言いたいことがそれぞれ出てくるだろうと感じた。どちらの側の思いも察しながら,「子供たちのために今後どうすればよいか」という共通の目的を見失わずに話合いを進めることが大切だと改めて感じた。
○架空のいじめ事例では,いじめた側もいじめられた側もどちらも悪いと思う。ただ,実際に保護者の耳に入るのは,「AさんがBさんにいじめられている。」という情報なので,その時に,一方的な情報だけを信じず,冷静に判断するようにしたい。
○事例を通じて,保護者側だけでは気付けなかった学校の先生側の気持ちや行動についても考えることができた。
○保護者も自分の感情だけでなく,子供自身の気持ちを引き出せるような関わりをしていくことが大切だと感じた。
○学校側の子供たちへの聞き取り方や保護者への伝え方などによっても,受け取り方やその後の関係性が変わっていくと感じた。
○いじめた側の保護者は,まずはそれを受け入れて謝ることが大切。いじめられた側の子供を気遣う言葉も伝えることで,その後の子供たちの関係も修復しやすくなる。
○何がいじめとなるのか分からない現代において,親子での会話を大切にできる家庭が増えたらいいなと思う。
○子供たちが学校で落ち着いて話を聞けたり,意欲的に物事に取り組めたりするように,睡眠などの生活リズムを整える意識をもてるようになれば,「他人の気持ちに寄り添う心の余裕」ができると思う。
○子供たちは,以前されていやだったことを急に思い出すことがあるが,それを話し始めた時には,その思いに共感することが大事だと感じた。
○皆さんの意見を聞いて,子供の気持ちに寄り添い共感することが大事だなと感じた。
○ささいなことでも相談しやすい雰囲気を大人がつくってあげたい。
○自己肯定感の低い子供たちがいるので,その子供たちが自分のことを認められるように関わっていきたい。
○いじめはつらい。いつの年代になっても起こること。児童の皆さんの悩み・つらさはなおのこと。少しでも力になれるよう,日々,自分のできるところで考えていきたい。
○グループワークでの話合いは意見が出ていい。「子供が主役」と考えて,全体で意見交換できる場を増やせればいいのではないか。
○心の育て方をどうしていくか(自分自身を認める心,相手を認める心など)。それらを学校・家庭・地域の3者で共有していくことが大事。大人も子供も同じ立場であると思う。
○子供たちにもっと強くなってもらいたい。自己主張ができるように。